私の百名山 −その7−
伊豆の踊り子・天城越えの
天城山(1,405m)
文学部 中條 保
伊豆山系の総称として
「天城山」も他の多くの山と同じように単独峰の名称ではなく、万二郎岳、万三郎岳を中心に遠笠山、箒木山など1,000mクラスの伊豆半島の背骨を成す山脈の総称としての呼称であり、なかでも最高峰の万三郎岳(1,405m)を天城山の盟主として百名山では数えている。
地理的位置と特徴
静岡県の東部、神奈川県と接する辺り、富士、箱根火山脈の南部に位置し駿河湾へ盲腸のように突き出した伊豆半島の中央部分にある。交通機関は「熱海」から「伊東」に下り、そこからバスで天城高原ゴルフ場の終点まで入る。これが一般的だが半島の中央部分「三島」から伊豆箱根鉄道の電車に乗り換え「修善寺」に下り、そこからバスで「天城峠」まで入るルートがある。往き、還りの選択は、日程や宿泊場所、交通機関との相談で判断すればよく、いづれの方から入っても特別な難路はなく、時間が許せば縦走すると良い。
かつて、天城は火山
地理的状況からも判るように伊豆半島は、富士、箱根と連続する火山脈の上にあって、天城山もかつては噴火して出来た山なので、途中の谷間の河川はどこも水が伏流していて飲料水の確保がままならぬ。とくに夏場など喉の乾く季節には十分な水分の準備が必要だ。もちろん麓には天城山系の水を集める狩野川が天城峠から北流して、途中に「浄蓮の滝」を作り、一方、峠を南下する河津川は「河津七滝」を形成し、豊かな清流はいづれも駿河湾に注いでいる。
伊豆はドラマティック
伊豆の天城は、麓を流れる狩野川に沿って古くから修善寺、湯ケ島、河津川に沿って湯ケ野の温泉街が開け、関東からの地の利も良くて文人墨客や湯治客が滞在し、歴史や小説、芝居や歌の舞台にもよく登場し、そのことがさらに観光客を集め、戦後の高度成長期にかけては、新婚旅行コースとしても多くの国民をひきつけた。古くは源頼朝の流刑の地として、近くは川端康成の小説「伊豆の踊り子」や近江敏郎が歌った「湯の街エレジィ」は戦後のヒット曲として、今でもナツメロとして往年の若者に愛唱されている。最近では石川さゆりの歌う「天城越え」で若者にも知られるようになった。また、半島の最南端に位置する下田は、黒船の来航とともに幕末から明治へと開国して行く日本の夜明けの舞台となった歴史上の重要な場所としても有名である。
10代の最後に彼の地を訪ねる
代最後の年に私は伊豆を旅していた。一碧湖や大室山、戸田や堂ヶ島、達磨山に遊び、天城越えをして下田を訪ね、そこから伊豆の大島に渡ったことがある。当時は百名山のことは知らず、伊豆にこれほどの名山があるなどつゆ知らず。よもやこうして百名山のために再訪する機会を得るとは思いもよらぬことであった。

夏に三島から入る
98年の夏、熱海での所用を利用して天城山に登る。金曜日は休暇を取ってJRで名古屋から三島へ。そこから一時間に3本ある比較的便利な伊豆箱根鉄道に乗り換え修善寺に出る。バスはすぐにあったので駅周辺を見学する時間もない。バスは狭い温泉街の路地を曲がりくねって橋を渡り、次第に天城の山奥に入って行く。浄蓮の滝でも下車客がいた。国道414号は、かつて「踊り子」の歩いた下田街道であるが、今は自動車時代に合わせて道幅もカーブも広く整備が進んでいる。天城トンネルも旧トンネルの下に広く、新しく開通していて、そのトンネルの入口で私一人が下車する。時計は14時15分になっていた。高山なら目的地に到着する時間だ。

天城峠へ
バス停脇の案内板を見るまでもなく、道路の左手を急な山道がトンネルの上部へと続いている。坂道を登って行くと若いアベックが下りてきた。10分ほど登ると旧天城トンネルの入口にたどり着く。乗用車が数台停まれるスペースがあって、トイレと東屋がある。私も観光客に混じってシャッターを切る。車で来ている観光客は入れ替わり、立ち替わりで、根強い人気スポットのようだ。トンネルを覗いてみるとテールランプの赤い色が鮮やかに暗闇に消えていった。
天城峠
旧トンネルの右手の沢に沿って登って行く。入口の薄暗さと対照的に左右にカーブを切って高度を増して行くと、50年生ほどの杉の植林に混じってブナ、クルミ、モミジの明るい疎林が開け、緑葉が茂っているが秋の紅葉を想像させる。足下は昨夜の雷雨に洗われて深い水の溝ができている。さすがにこちらは人影もない。旧トンネルからわずか15分の登りで到着した天城峠には太いブナの巨木があって驚かされる。天城縦走路の標識が整備されていて心配ない。「仁科峠へ14.4Ɠ、旧天城峠へ3.9Ɠ」の標識を見て、地図で確認しながら休憩用のベンチに荷物を下ろして休憩する。15時10分出発。

八丁池へ
今日の目標地点はこの池である。水場があってもなくても、ここに露営する予定である。この峠から池への道は、広い水平道で太いブナと赤いヒメシャラが印象に残る稜線で根元にはスズタケが茂っている。この竹もヒメシャラも数年前に箱根の山で見かけたのが最初で、ヒメシャラは一昨年訪れた屋久島にも多かった。誰もいないと思って歩いていると峠から10分ほどの辺りで男女4人の軽装者とすれ違う。向峠を15時35分に通過する。最近、歩行中は携帯ラジオを聞きながら歩いているので、ちょうど高校野球の実況放送で豊田大谷が9回裏に同点に追いつき、延長10回裏で2アウトからさよならゲームとする。高校球児の活躍を感動をもって聞きながら、「たかだか歩くだけの単純な我が山登りに困難はない」などと自らを励ましながら、それでも写真を撮ったり、早朝の出発と発汗で疲れが出てきた体に水ようかんとお茶を与えて、だましながら思ったより時間のかかる日程に奮戦する。
八丁池
池の手前の高台に展望台がある。その鉄骨製の展望台へはアセビの老木が左右から覆いかぶさるようなトンネルを抜けて鉄板の階段を登る。あたかも天城の山系を上空から見渡すようだが、あいにくガスがかかっていて視界は時折開けるが2〜300m程度。富士山も駿河湾も見えず残念である。そのうちに足下の八丁池にもガスがかかってくる。池の畔の東屋を確認しておいたので、その方角に急いで下って行く。火口湖である池はモリヤアオガエルの生息地で周囲が八丁(870m)あるところから付いたそうな。17時40分に到着する。ガスはすっかり池を覆い、今にも雨が降り出しそうな気配である。早速に東岸の東屋の脇にテントを張る。誰一人として出会わぬ静寂の池の畔で、準備してきたワカメとタマネギ入りのラーメンを食べ、京都、常総学院の対戦を聞きながら18時30分に就寝する。夜半の激しい雨音に目覚めると、まだ10時過ぎである。それから30分ほどスコールのように続いた雨も止み、「キーン」という鋭い鹿の鳴き声を聞きながら再び眠りに就く。
起床、出発
午前5時起床。雨は上がり、霧の立ちこめる池で顔を洗う。朝食は昨夜と同じメニューで、今日の昼食も同じで3食ともラーメンだ。初めての道で、暗い内の出発は迷いやすいのと雨上がりの草丈でズボンが濡れるのも難儀だし、テントも濡れているので出来るだけ軽くしたい。そんなこんなで6時30分十分明るくなるのを待って出発する。マッチの棒一本落とさぬように、先客の落としたゴミも拾って出発する。自然の中では当然のマナーである。
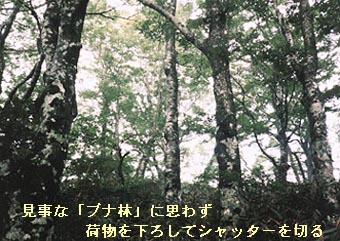
万三郎岳へ
出発して40分、ブナ林があまりにも美しいので荷物を下ろして写真を撮る(5分間)。「戸塚峠へ25分、八丁池へ40分」の分岐を通過する。戸塚峠に8時05分着。「白田峠へ1.6Ɠ、小岳へ1.3Ɠ」の標識有り。ブナとヒメシャラにシャクナゲやアセビ(ツツジ科)が混じってくる。小岳(戸塚山)に9時07分到着する。広い山頂はブナを中心に20mほどの立派な森に覆われていてベンチがある。緩やかで広い直角の路なりが山頂である。迷いやすいが緩やかに左手に下って行くので、ゆっくり確認すれば間違わない。万三郎へは小岳からワンピッチ50分で到着する。下りきった鞍部から、少し足場が悪い急な石の階段を5〜6回廻るように登るようにして登り切ると万三郎の山頂に出る。このコースで唯一最大のダウン・アップの案部を越える。

万三郎岳
午前10時ちょうどに到着し、甘いものとお茶で休憩をしていると反対側から青年が2人登ってきた。愛知県の豊橋から昨夜出発して国道を走り修善寺から伊豆スカイラインに入り、林道の終点で車の中で眠って、今朝歩いて来たという。さすが若者、結構容易くこれるものだ。この山頂でも霧のため富士山は見えず、10分の休憩の後、出発すると中年の夫婦が登ってくるのと出会う。
万二郎岳(1300m)
少し急な下りもすぐに広く平らなアセビの連続する森の中を行く。シャクナゲの老木が多くなると万二郎は近い。左に直角にカーブした角っこが山頂だということが標識がなければ判らない。その手前に中年の夫婦が食事をしていたので山頂が近いとは感じたが。さて、ここで私は左手に折れて天城高原ゴルフ場のバス停に行くべきか、右手の箒木山に行くべきか迷っていた。バス停へは1時間足らずのワンピッチで到着できる。一方の箒木山へは、地図上の道が無い。しかし、等高線は少し急傾斜だが鞍部を挟んで尾根伝いに連続している。クマザサをかき分け万二郎岳のピークを東に下ってみる。かろうじて踏み跡らしきものはある。再度地図を広げて再考する。
箒木山(1023m)へ
最近は人が歩いていない急斜面では、踏み跡が消えているが、所々に古いテープが付いていて助かる。下りかけて5分位で急斜面に出会い、古いザイルが取り付けてあり、これに導かれて下る。滝への案内石で少し迷うが基本は二つのピークを結ぶ尾根筋を行くことだ。谷筋に下りてはいけない。そう言い聞かせて、木の間隠れの箒木山を確認しつつ注意深くルートを選んで下って行く。25分の下りの何と長く感じられたことか。緊張感も加わり汗びっしょりだ。12時ちょうどにピークを前にした鞍部に到着する。「奈良本」へ下る「中道」の表示に出会い安堵する。夏草が覆うNTTの通信塔のあるピークをあきらめ林道に下ることにする。
昼食後、伊豆大川へ
昼なお暗い杉の植林が連続する下りは、ルート表示が全くなく、林道作業も放棄されていて判りづらい。かなり長く感じられたが20分で林道に出る。ちょうど土木作業用のトラック3台が左手に向かうので「大川」への道を尋ねると「どちらでも行けるが左が良い」という。半信半疑で未舗装の林道を行くと箒木山のNTT無線中継所の入口に出た。本当ならここに下ってくる予定だった。ゲートの前で地図を出して現在位置を確認する。時間も12時55分になっていたので昼食にする。この間、滝や沢、谷間を幾つも超えてきたが、一滴の水も手に入らなかった。3.5リットル持参した最後の飲料水300ccを飲み干す。したがってラーメンは林道脇の側溝の水が比較的澄んでいたので、これを静かに汲んで使用するしかない。濡れたものを乾かしながら昼寝も入れて1時間20分の休憩を取る。
大川から熱海へ
大きな山容の箒木山の東面を眺めながら、舗装された林道を駿河湾目指してドンドン下る。飲料水を求めるが入手できず。1時間40分歩いて「大川花の遊歩道」に着くと下草刈り中のおじさんが近くに水場があるという。「名水」の表示のある湧き水は、チョロチョロと流れていて、それでもありがたかった。リュックをおろして腹一杯飲む。そこへ麓の「大川館」の主がバイクで通りかかり談笑する。「冬は鹿狩りをするという」。初夏のシャクナゲの咲く頃は観光バスを連ねてゴルフ場から「人の波」で登り、下りの長い列で渋滞するという。ミカン畑の急坂を下り民家の前を抜けると「伊豆大川」の駅に着く。踏切の遮断機が降り警報機が鳴っている。熱海まで1200円也の切符を買うのも危うく16時43分発の電車に乗ると同時に出発する。車内は海水浴で疲れたアベックが3組ほど乗っている。17時50分に熱海駅に到着する。疲れた体を励まして、駅前から歩いて10分のホテルにたどり着く。さっそく、まだ明るい温泉に浸かり、疲れと汗を流し、駿河の海を眺めてくつろぐ、また楽しからずや。至福の一時である。湯上がりのビールのうまさはもちろんのこと。言うには及ばない。
 前頁
前頁  次頁
次頁
教職員委員会 私の百名山
kyosyokuin@coop.nagoya-u.ac.jp
 前頁
前頁  次頁
次頁



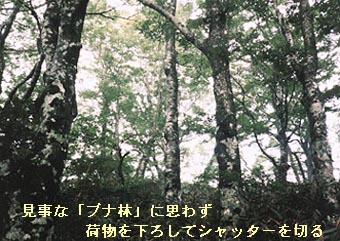

 前頁
前頁  次頁
次頁